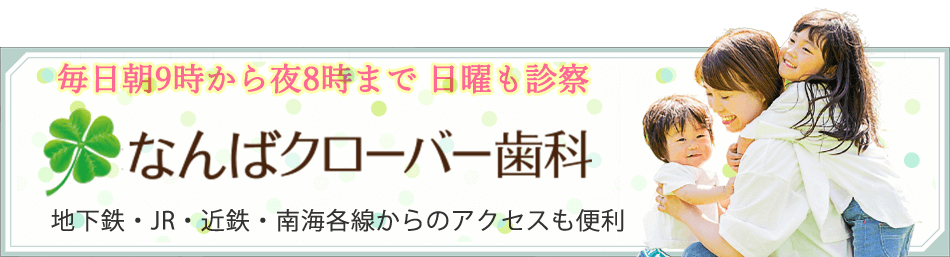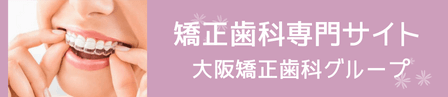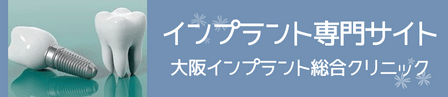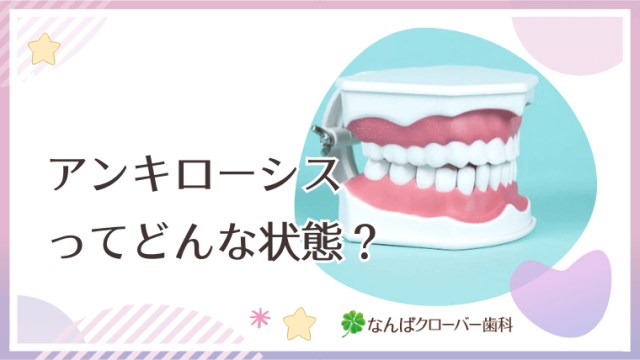歯茎が痩せたのを戻すことは出来る?

歯茎が痩せたのを元に戻す方法はないのかと、歯磨きしている時にふと思うことはありませんか。今日は、歯茎が痩せた原因と、歯茎を戻す方法について詳しくご紹介いたします。
歯茎が痩せた原因
歯茎が痩せた、下がったと言われる原因について、挙げていきましょう。
歯周病になっている
成人した日本人の8割が、程度は違えどかかっていると言われるのが歯周病です。口腔内には様々な菌が存在していますが、歯周病の発症を起こす菌として有名なのが下記の菌で、それらは1種類のみ見つかることはなく、併せて見つかることが多いです。
P.g菌 (Porphyromonas gingivalis)
歯周病を重症化させる代表的な菌で、歯周病菌の中でも毒性が強いとされています。体内の免疫応答を調節する能力を持っているため、炎症をより重く進行させます。
A.a菌 (Aggregatibacter actinomycetemcomitans)
若い年齢層でみられる若年性歯周炎の原因菌として知られています。侵襲性が高く歯周組織を破壊する力が強い厄介な歯周病菌です。
P.i菌 (Prevotella intermedia)
歯周病の炎症を悪化させる作用があり、特に思春期や妊娠中に増殖しやすい傾向があります。
ブラッシングを間違えている
強い力で角度を間違えてブラッシングを続けていると、歯垢(プラーク)や食べかすを除去できないばかりではなく、歯肉が擦過傷になります。擦過傷の部分を安静にしないまま同様の歯磨きを行っていると、歯肉を退縮させてしまいます。
噛み合わせが悪い
全部の歯ではなく一部の歯が強く噛んでしまっている場合、特定歯に過剰な力がかかります。特定歯のそばの歯茎にも負担がかかり、歯茎下がりを起こしてしまいます。歯ぎしりや食いしばりが癖である方も無意識下に噛みしめすぎてしまい、歯茎の退縮を引き起こします。
加齢による
加齢により若い時よりも新陳代謝が衰えて骨密度が下がると、歯を支える歯槽骨の骨密度も減ります。骨密度以外に歯茎の弾力や厚みを保つコラーゲンが低下すると、歯茎の退縮が起きます。
タバコを吸う習慣がある
喫煙をすると、一酸化炭素やニコチンが体内に摂取されます。それにより、血流が悪くなると、歯肉維持のための栄養素が行き渡りません。栄養不足になるとどうしても免疫力は低下し、それにより歯周病にかかりやすくなります。
それは歯周病かも?
それは歯周病かもしれないというサインをご説明します。
初期段階
初期段階は歯茎が赤く腫れていて歯肉炎という段階です。健康な歯ぐきは薄いピンク色ですが、炎症が起こると赤くなります。歯磨きやデンタルフロスを行うと出血してしまい、歯ぐきがむずむずしたり、違和感がある状態です。
中度
中度の歯周病になると、毎回出血が起こり、歯周病菌が出すガスや膿が原因である口臭が起こりやすくなります。また、歯が長く見えるほど歯ぐきが下がったり、歯と歯の間に食べ物が詰まりやすいなどの自覚症状があります。歯周組織を破壊されることが多くなります。
重度
歯を支える骨が大きく溶けてしまった状態で歯茎が痩せてしまい、グラグラすることがあります。歯ぐきに膿の袋であるフィステルができてしまい、それにより強い口臭が出ます。噛んだときに痛かったり、噛みにくいという症状があります。
口の中のネバネバ感や、歯茎のラインが水平ではなくなったり、全体的に歯が浮いた感じがする場合も歯周病である可能性があります。
歯茎を元に戻す方法は?
歯ぐきがやせてしまう原因は様々ですが、一度やせた歯ぐきは、自然には完全に元には戻りません。ただし、進行を止めたり、改善することは可能です。
進行を止め、これ以上歯茎をやせないようにする方法
進行を止めるためには、家で行うセルフケアと歯科医院で行うプロのケアの両方が必要となります。
セルフケアで行うこと
正しいブラッシングをしましょう。柔らかめの歯ブラシで、優しく磨いてください。鏡を見て毛先がきちんと当たっているか確認し、ゴシゴシ磨きはNGです。また、ストレスがかかり過ぎている状態では、免疫力が低下しどうしても炎症が起こりやすくなるため、ストレスのかからないリラックスする環境を作りましょう。
プロに行ってもらうこと
歯周病が原因の場合はまずは歯周病の治療が最優先で、歯茎の検査後、歯石除去やクリーニングをし、歯茎の再検査をします。中度の場合は、歯周ポケットの深い部分の歯石除去をして、歯茎の再検査となり、重度の場合は外科的処置(フラップ手術、再生療法)、ブルーラジカル治療などが必要となります。歯周病の治癒が認められたら定期的メインテナンスをして予防をします。プラークコントロールと定期的なクリーニングが歯周病を再発させないカギとなります。
歯ぎしりや食いしばりが口腔態癖としてある場合は、就寝時に装着するマウスピースを作製してもらい、歯茎への負担を減らします。
改善する方法
歯茎を外科的に改善する方法としては、歯周組織の再生療法や歯肉移植が効果的です。
再生療法
再生療法として認められているのがGTR法とリグロスとエムドゲイン法です。歯茎を移植する手術もあり、見た目や知覚過敏の改善に有効ですが、外科的処置であるため、診断と計画が必要です。
GTR(Guided Tissue Regeneration)法
歯周ポケット内の歯垢や歯石を除去し、骨が痩せた部分に人工膜(メンブレン)を挿入し、歯槽骨や歯根膜の再生できるスペースを作る治療法です。歯槽骨や歯根膜の再生が成功すると、自然と骨の高さが上がるため、歯茎の改善を期待するという治療法です。
リグロス
歯根の表面に付着した汚れを除去した後、細胞を活発化させるbFGF(塩基性線維芽細胞増殖因子)が含まれたリグロスという薬剤を塗布します。細胞の増殖や分化を促進する成長因子で、血管内皮を新しくし、歯周組織の再生に大きくかかわります。
エムドゲイン
歯茎を切開して、汚れを除去したあと、豚の歯胚から抽出し精製したタンパク質(エナメルマトリックスデリバティブ)を含むジェル状の薬剤です。歯が生える時と似たような環境にすることで、歯周組織の再生を期待でき、手術が一回のみで終わることが多いです。ただし、自費診療となるため、費用はリグロスやGTR法に比べて負担額は高いです。
遊離歯肉移植術
上あごの内側の部分のかたい歯肉を採取して、やせた部分に移植する方法です。治療痕が見えることもあるため、前歯よりも奥歯に効果的です。
歯茎が痩せたりしないためにはどう予防?
歯茎が痩せたりしないためにはどう予防すればよいでしょうか。
- 柔らかめの歯ブラシで小刻みに正しいブラッシングを心がける
- 定期的に歯科検診でクリーニングを受け、プラークコントロールを心掛ける
- 歯ぎしりや食いしばりは過度な力がかかるため、就寝時にナイトガードを装着し日中も気を付ける
- 喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ歯周病リスクを高めるため禁煙する
- バランスの良い食事や睡眠で歯ぐきの健康を維持し、ストレス管理をする
まとめ

歯茎が痩せたら自然には戻りませんが、手術で改善する方法はあります。ただし、歯茎を上げる外科手術よりも、静かに進行する歯周病の進行を食い止める必要があります。初期には痛みがほとんどないため、気づきにくいのが特徴で、これらの症状に気づいたら、早めに歯科医院で診てもらうことが大切です。