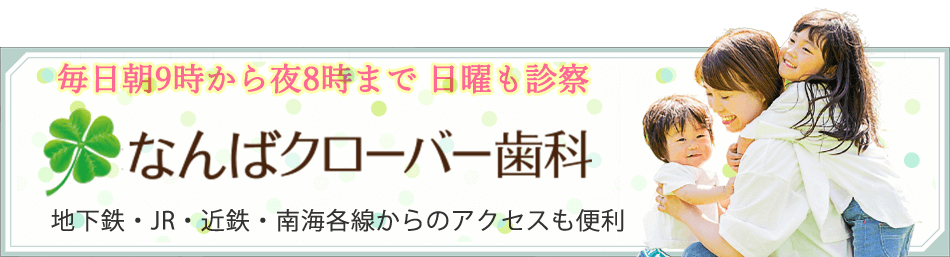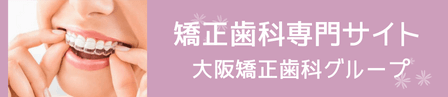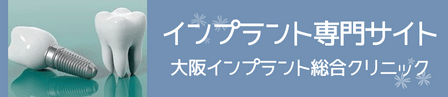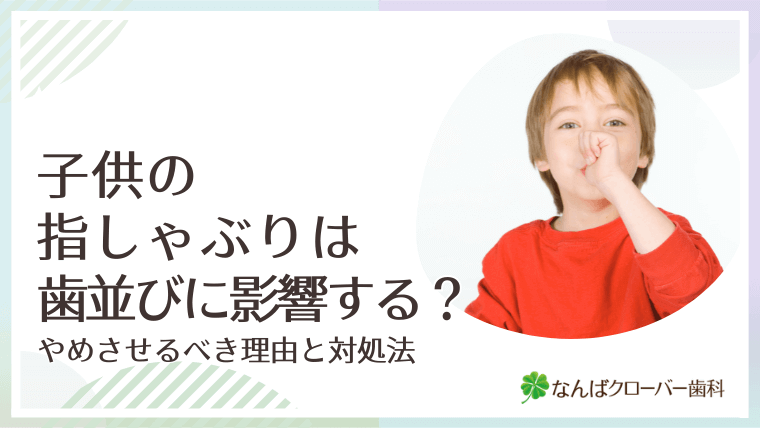
「子供の指しゃぶりは歯並びへの影響のためにもやめさせるべき?」
この疑問に対しての答えは「はい、できるだけ早くやめさせるべき」です。
指しゃぶりは赤ちゃんにとって安心材料のひとつですが、長く続くと歯並びや顎の発育に悪影響を与えることがあります。この記事では、特に3歳以降の指しゃぶりがもたらすリスクと、やめさせるための具体的な工夫について、歯科の視点からやさしく解説します。
この記事はこんな方におすすめ!
- 子供の指しゃぶりが気になる保護者の方
- 歯並びへの影響が心配な方
- 無理なくやめさせる方法を知りたい方
この記事を読むとわかること
- 指しゃぶりが歯並びにどう影響するか
- やめるべき時期とタイミング
- 子供へのやさしいやめさせ方
目次
指しゃぶりは歯並びに悪影響を与えることがある
指しゃぶりの習慣は、特に永久歯への生え変わり期に影響を及ぼす可能性があります。
乳幼児期の指しゃぶりは自然な行動ですが、これが3歳を過ぎても続くと、次のような問題につながることがあります。
- 上の前歯が前に出る(出っ歯)
- 上下の前歯がかみ合わない(開咬)
- 顎の発育バランスの乱れ
その結果、将来の不正咬合の原因となり、矯正治療が必要になることもあります。
指しゃぶりが与える「力」とは?
指しゃぶりによって指が口の中に入ると、前歯や上あごに繰り返し力がかかります。特に影響を受けやすいのが上の前歯。指が前歯を押すことで、歯が前方に傾きやすくなります。
- 前に出る力(前突)
→ 上の前歯が外向きに出て、出っ歯のようになる - 上下の歯の間にできる隙間(開咬)
→ 上下の前歯がかみ合わなくなり、隙間ができる
指が常に口に入っている状態が続くと、口の周囲の筋肉バランスにも悪影響を及ぼします。例えば、口を閉じる力が弱くなったり、舌の位置が不安定になったりすることで、かみ合わせ全体に悪影響が出ることもあります。
「乳歯だから大丈夫」は間違い?
「乳歯は生え変わるから指しゃぶりの影響は心配いらない」と思われがちですが、乳歯列期にかかった力は、顎の骨の成長方向にも影響を与えます。
つまり、歯が生え変わっても、顎の形そのものがゆがんでしまうと、永久歯の歯並びにも問題が出るリスクが高まります。
歯並びの乱れだけじゃない!他にもある悪影響
歯並びだけでなく、以下のような影響も出る可能性があります:
| 悪影響 | 内容 |
|---|---|
| 発音障害 | 「さ行」「た行」などの発音が不明瞭になる |
| 嚥下異常 | 舌の使い方が不自然になり、飲み込みがぎこちなくなる |
| 鼻呼吸の妨げ | 指しゃぶりによる口呼吸の習慣がつくこともある |
成長期は「骨格」にも影響を与える
指しゃぶりは、単に「歯」だけでなく、「骨格の成長」にも関係しています。3歳〜6歳ごろの子供の顎の骨は、やわらかく、外からの力の影響を受けやすい状態。
特に上顎は、指による「上方向」「前方向」の力を受けやすく、成長にゆがみが生じやすくなります。放置すると、口元全体のバランスが崩れることもあります。
長引く指しゃぶりは、将来の歯並びや口腔機能に関わる重要な要素です
- 指しゃぶりが長引くと、出っ歯・開咬・顎のゆがみなど、さまざまな不正咬合のリスクがあります。
- 乳歯の時期でも骨格に影響を与えるため、歯が生え変われば治るというわけではありません。
- 歯並びだけでなく、発音・嚥下・呼吸といった機能にも悪影響が出る場合があります。
お子さんの指しゃぶりに気づいたら、あたたかく見守りながら、少しずつサポートしてあげることが、将来の健康な歯並びと口元の成長につながりますよ
悪影響が出やすいのは3歳以降
幼児期のうちにやめることが望ましく、特に3歳以降は歯並びへの影響が現れやすくなります。
指しゃぶりが一時的であれば問題は少ないですが、以下のようなタイミングを過ぎると、歯や骨の形に影響を与えるリスクが高まります。
- 3歳頃 → 上下の乳前歯がかみ合い始める時期
- 5歳頃 → 永久歯の準備が始まり、顎の発達も加速
- 6~7歳 → 永久歯の萌出が始まる時期
このように、成長の段階に応じて、影響の度合いも変わってきます。
どんな歯並びのトラブルが起こるのか
指しゃぶりによる圧力が、前歯や顎の形に影響を与えてしまいます。
代表的な歯並びのトラブルは「出っ歯」と「開咬」です。
代表的なトラブルの例
| トラブル名 | 内容 | 原因と関係 |
|---|---|---|
| 出っ歯(上顎前突) | 上の前歯が前に傾く | 指をくわえることで前方に圧がかかる |
| 開咬 | 上下の前歯がかみ合わない | 指が常に前歯の間にある状態が続く |
| 上顎の狭窄 | 上顎が横に広がりにくい | 指の押し上げによる骨格発達の妨げ |
これらの症状は、発音や咀嚼(噛む)にも悪影響を及ぼし、将来的に矯正治療が必要になるケースも少なくありません。
やめさせるための具体的な工夫
無理なく自然にやめられる工夫を、年齢や性格に応じて取り入れましょう。
怒ったり強制するよりも、肯定的なアプローチが効果的です。
やめさせるための主な方法
- 「卒業する日」を子供と決めてカレンダーに記入する
→ 子供に自分でやめる意志を持たせられます。 - 寝る前の代替手段(ぬいぐるみを抱かせるなど)を用意
→ 安心感を得る手段を変えることで、指しゃぶりをやめやすくなります。 - できた日にはシールや褒め言葉でごほうびを
→ 成功体験がやる気につながります。 - 指に絆創膏を貼って気づかせる
→ 無意識の指しゃぶりを意識させる効果があります。
これらは、子供の自主性と安心感を守りながらやめさせるためのアプローチです。無理に叱ると逆に不安が強まり、習慣が長引くこともあるので注意しましょう。
指しゃぶりは「無理やりやめさせる」よりも、子どもが納得して“卒業”できる工夫が大切です。お子さんの性格をふまえて、“褒める関わり”や“卒業日カレンダー”など家族と一緒に楽しく取り組むことを推奨しています。成功体験を積むことで、歯並びだけでなく自己肯定感も育まれると私自身実感しています。
焦らず親子で乗り越えるための心構え
指しゃぶりをやめるには、親の接し方も大切なポイントです。
子供の気持ちを尊重しながら、根気強く取り組むことが大切です。
指しゃぶりは安心のサインでもあります。やめさせることに焦って、
「まだやってるの?」
「もう赤ちゃんじゃないでしょ」
などの否定的な言葉をかけると、逆効果になることがあります。
子供の不安やストレスを減らす環境づくりと、前向きな声かけがとても大切です。
歯科医院での相談も大切な選択肢
どうしてもやめられないときは、歯科医院に相談してみましょう。
専門家のアドバイスで、より適切な対処ができます。
歯科医院では、
- 指しゃぶりによる歯並びの影響の評価
- 必要であればマウスピースなどの装置の提案
- 保護者への対応アドバイス
など、専門的なサポートが受けられます。長引く指しゃぶりに不安を感じたら、早めの相談が安心につながります。
まとめ
指しゃぶりは、3歳以降は歯並びへの影響を考えてやめさせるべき習慣です。
子供の気持ちに寄り添いながら、焦らず少しずつ進めていくことで、自然とやめられる可能性が高まります。そして困ったときには、歯科医院も力強い味方です。