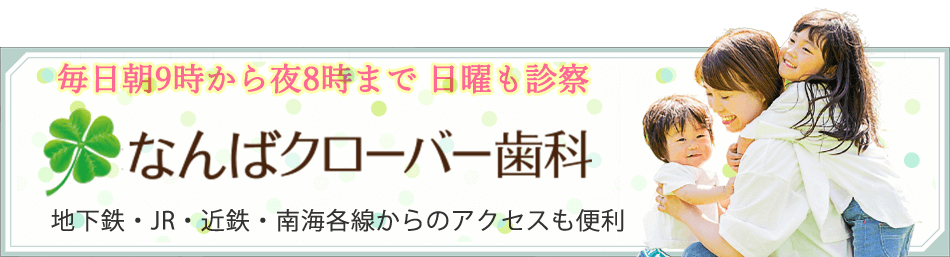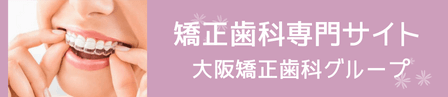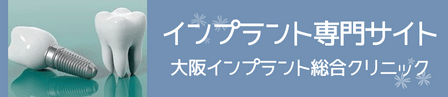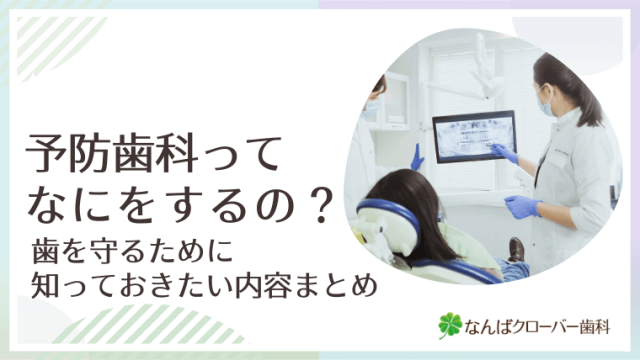歯石ができる原因やリスクについて
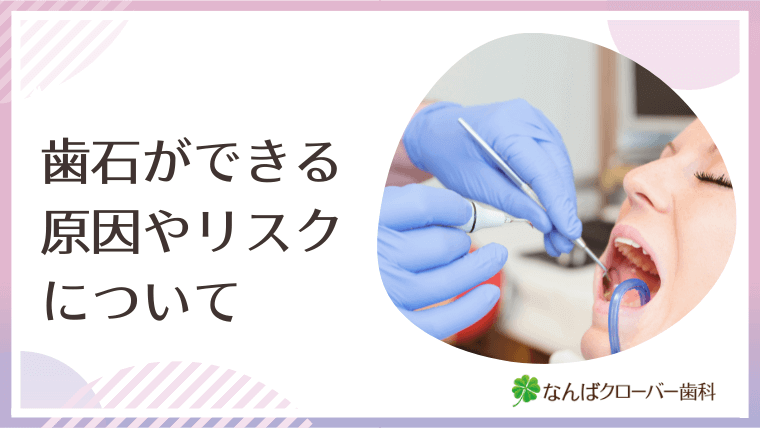
「最近、歯がザラザラする気がする…」
「歯磨きをしているのに、なんだかスッキリしない…」
こんな風に感じたことはありませんか?
実は、それは 歯石 が原因かもしれません。
毎日しっかり歯磨きをしているつもりでも、気づかないうちに歯石ができてしまうことは珍しくありません。
「どうして歯石ができるの?」「放っておいたらどうなるの?」
そんな疑問や不安を抱えている患者さんも多いのではないでしょうか?
歯石は 一度できてしまうと歯磨きでは取れず、放置すると歯や歯ぐきに深刻なダメージを与える ことがあります。でも、正しいケアを知ることで予防することが可能です!
今回は、 歯石ができる原因やそのリスク について、分かりやすくご説明していきます。
目次
歯石とは?
歯石は「歯垢」が硬くなったもの
歯石とは、歯垢(プラーク)が硬くなり、歯の表面にこびりついたもの です。歯垢は、食べかすや細菌の塊で、日々の歯磨きで取り除くことができます。しかし、磨き残しがあると、時間とともに唾液の中の カルシウムやリン酸と結びつき、石のように硬くなる のです。
歯石は 自分では除去できず、歯科医院での専門的なクリーニングが必要 になります。放置すると、歯や歯ぐきに悪影響を与え、さまざまなトラブルを引き起こす原因になります。
歯石の特徴
色や場所によって2種類に分類される
歯石には、発生する場所や状態によって 「歯肉縁上歯石」 と 「歯肉縁下歯石」 の2種類があります。
1. 歯肉縁上歯石(しにくえんじょうしせき)
歯ぐきより上の部分(歯の表面)にできる歯石
黄色〜黄褐色の見た目 をしており、目で確認しやすい
比較的やわらかく、超音波スケーラーなどの機器で除去しやすい
磨き残しが多い場所(前歯の裏側や奥歯)にできやすい
2. 歯肉縁下歯石(しにくえんかしせき)
歯ぐきの下(歯周ポケットの奥)にできる歯石
黒っぽい色をしている ことが多く、目では見えにくい
非常に硬く、こびりつきが強い
歯周ポケットの奥にあるため、気づかないうちに歯周病が進行するリスクが高い
このように、目に見える歯石だけでなく、気づかないうちに歯ぐきの中に歯石がたまることもある ので注意が必要です。
歯石ができるまでの流れ
歯石は、一夜にしてできるものではありません。段階を踏んで形成されていきます。
- 歯垢(プラーク)の付着(1日目)
→ 食後、磨き残した部分に細菌が集まり、白くネバネバした歯垢 となる。 - 歯垢が蓄積(2〜3日目)
→ 歯磨きが不十分な部分にどんどん歯垢が増える。 - 歯垢が石灰化(3〜5日目)
→ 唾液中のミネラルが付着し、少しずつ硬くなり始める。 - 完全な歯石になる(7日〜10日以降)
→ 完全に硬くなり、歯磨きでは取れなくなる。
歯石は、歯垢が硬くなってできるものです。特に、3日以上放置すると石灰化が始まり、1週間〜10日ほどで完全な歯石 になってしまいます。
つまり、歯石を防ぐためには、毎日の歯磨きで歯垢をしっかり取り除くことが重要 なのです!
ポイント
- 歯垢は歯磨きで落とせるが、歯石は歯磨きでは除去できない
- 歯石は細菌の温床となり、口内環境を悪化させる
歯石は、毎日のケアだけでは取り除くことが難しく、一度できてしまうと歯科医院での専門的なクリーニングが必要になります。
歯石ができやすい場所
歯と歯ぐきの境目
歯と歯の間
下の前歯の裏側(唾液の分泌が多い場所)
上の奥歯の外側(唾液腺が近く、歯垢が付きやすい)
特に、歯垢が溜まりやすい「歯と歯ぐきの境目」や「歯と歯の間」は、歯磨きだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシも活用することが大切 です。
歯石があるとどうなる?
歯周病が進行しやすくなる
口臭の原因になる
歯ぐきが炎症を起こしやすくなる
歯が黄ばんで見える
特に、歯石が長期間付着すると、歯ぐきの奥に入り込んで 歯周病の原因 になります。
また、歯石はザラザラしているため、さらに歯垢が付きやすくなり、悪循環を生む原因にもなるのです。
歯石ができる主な原因
歯石は、誰にでもできる可能性がありますが、特に次のような原因によって発生しやすくなります。
歯磨きが不十分
→ 歯垢がしっかり取り除けていないと、歯石へと変化しやすくなります。特に歯と歯の間、歯の根元、奥歯などは磨き残しが多い部分です。
唾液の成分や分泌量
→ 唾液には歯垢を洗い流す働きがありますが、唾液の分泌が少ないと歯垢が溜まりやすくなり、歯石の原因になります。
食生活の影響
→ 甘いものや粘着性の高い食品を多く摂ると、歯垢が溜まりやすくなります。また、柔らかい食べ物ばかり食べると、歯の自浄作用が低下し、歯石の形成が進んでしまいます。
歯並びや詰め物の影響
→ 不正咬合(歯並びの乱れ)や詰め物・被せ物の形状によっては、歯垢が溜まりやすくなり、歯石が付きやすくなります。
喫煙や口呼吸
→ 喫煙は歯にヤニがつきやすく、歯垢の沈着を助長します。また、口呼吸をすると口の中が乾燥し、唾液の働きが弱まるため、歯石ができやすくなります。
歯石の原因は生活習慣や体質など様々ですが、毎日の適切なケアと生活習慣の見直しで予防することが可能です。
歯石が引き起こすリスク
歯石は見た目が悪いだけでなく、お口の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。
歯周病の原因に
→ 歯石は細菌のすみかとなり、歯ぐきの炎症(歯肉炎)や歯周病を引き起こします。放置すると、歯を支える骨が溶け、最悪の場合は歯が抜けてしまうことも。
口臭の原因に
→ 歯石に潜む細菌が発生させるガスが、強い口臭を引き起こします。
虫歯のリスクが上がる
→ 歯石の下に隠れた虫歯は進行しやすく、気づいた時には神経まで達していることもあります。
歯ぐきが下がる(知覚過敏)
→ 歯石による炎症が進むと、歯ぐきが痩せてしまい、知覚過敏(冷たいものがしみる)を引き起こすことがあります。
歯石は、歯と歯ぐきの健康を脅かす存在です。見た目の問題だけでなく、長期的なお口のトラブルを引き起こすため、早めの対策が必要です。
歯石を予防するためのポイント
歯石を防ぐためには、日頃のケアがとても重要です。
正しい歯磨きを習慣化する
→ 歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、丁寧に磨きましょう。特に、奥歯や歯と歯の間は意識して磨くことが大切です。
デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
→ 歯磨きだけでは取りきれない歯垢を取り除くために、デンタルフロスや歯間ブラシを併用しましょう。
定期的に歯科医院で健診を受ける
→ 3〜6ヶ月に一度のペースで歯科医院を受診し、歯石の除去を行いましょう。
生活習慣を見直す
→ 唾液の分泌を促すために、水分補給やよく噛む習慣をつけることも大切です。また、喫煙や口呼吸の改善も心がけましょう。
毎日のケアに加えて、歯科医院での健診を習慣にすることで、歯石のリスクを減らし、健康な歯を保つことができます。
まとめ
歯石は、放置すると歯周病や口臭の原因になり、最終的には歯を失うリスクもあります。しかし、適切なケアと定期的な歯科受診を心がけることで、歯石の発生を最小限に抑えることができます。
歯石は 歯垢が硬くなったもの であり、一度できると歯磨きでは取れない
歯肉縁上歯石(歯ぐきより上)と 歯肉縁下歯石(歯ぐきの下)の2種類がある
3日以上放置すると石灰化が始まり、1週間〜10日で完全な歯石になる
下の前歯の裏側や奥歯の外側は特に歯石ができやすい
歯石が付くと、歯周病や口臭のリスクが上がる
「ちょっとザラザラするな…」と感じたら、早めに歯科医院でチェックを!
定期的なクリーニングで、健康なお口を守りましょう!