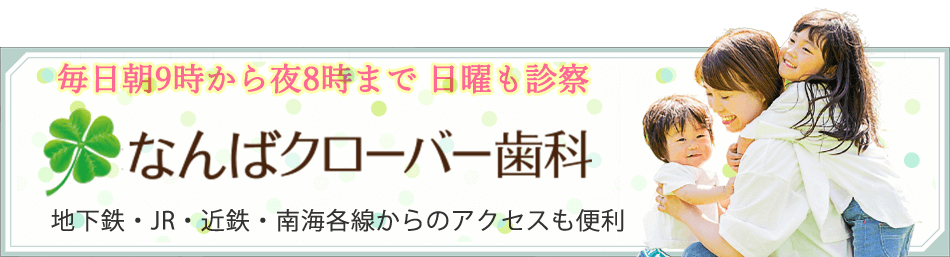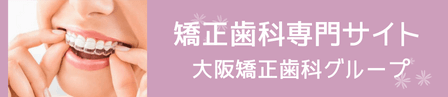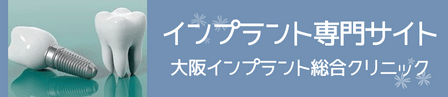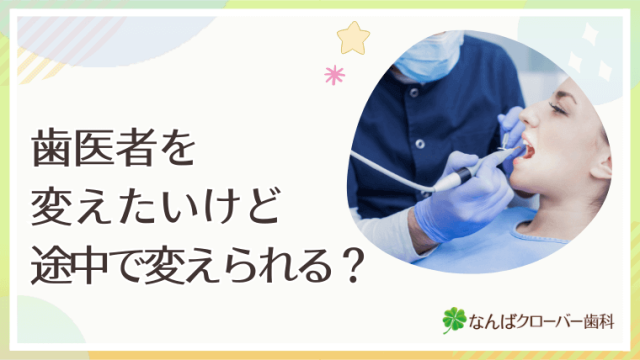歯の形が悪いのは放っておいても良い?

歯の形が悪いと気にされる方は多く、専門用語では、形態異常と言います。形が悪いまま放っておくと、形態異常の種類によっては、口腔機能に影響が出ることがあり、何かしらの治療を行うべきケースがあります。
歯の形態異常の種類
歯の形態異常についてどのような種類があるのか、詳しくご説明します。
- 矮小歯(わいしょうし)
- 巨大歯
- 癒合歯(ゆごうし)
- 癒着歯
- 歯の形成不全
- 結節の異常
- 歯根の形態異常
矮小歯とは
矮小歯とは、通常の大きさよりも明らかに小さい永久歯や乳歯のことを指します。形状が縮小していたり、細く尖っていることがあり、歯の先端が円錐状になることが多いです。
特に多く見られやすい位置は、上顎側切歯(上の前歯の隣の歯)で、次いで第三大臼歯(親知らず)です。
✅ 原因
- 家族に同じ症状を持つ人がいる遺伝的要因
- 歯の発達過程で何らかの影響を受け、形や大きさに異常が現れる発育異常
- ダウン症や先天性梅毒などの全身疾患
✅ 影響
- 審美面:前歯に矮小歯があると、見た目に違和感が生じやすい
- 噛み合わせの乱れ:隙間が空くことで他の歯の位置がずれ、咬合(かみ合わせ)に悪影響を及ぼしやすい
- 不正咬合の原因:矮小歯のスペースに隣の歯が倒れ込み、歯列が乱れることがある
- 発音や咀嚼への影響:特に前歯の場合、タ行や作業の発音障害や食べづらさにつながることがある
巨大歯とは
巨大歯とは、通常の歯よりも極端に大きな歯を指す歯の形態異常です。特定の1本のみが大きくなる場合や、複数本、歯列全体に影響すると、見た目の違和感のみでなく、歯並びや咬み合わせの問題を引き起こし、歯科的な管理や治療が必要になることがあります。顎が小さくて相対的に歯が大きく見えるケースもあります。
上の顎の前歯の真ん中(上顎中切歯)の平均の幅が男性で8.6mm、女性で8.5mm、歯の長さは10mm程度です。前歯の幅が10mm以上、長さが12mm以上であれば巨大歯と診断されることがあります。
✅ 影響
- 審美面:歯が顎に対して大きすぎて口元のバランスが崩れ、見た目の調和に悪影響を与える
- 噛み合わせの乱れ:周囲の歯のスペースが不足し、歯並びが乱れる叢生(そうせい)を引き起こす
- 口腔内の衛生状態:乱れている歯並びでは歯磨きがしづらく、虫歯や歯周病になりやすい
癒合歯とは
癒合歯とは、隣り合った2本以上の歯の卵(歯胚)が顎の骨の中で発育中にくっつき、1本のように見える状態の歯です。見た目は大きく幅広い歯になり、下顎の前歯(特に乳歯)に多く見られ、神経(歯髄)が歯の中で繋がっていることがあります。セメント質、象牙質、エナメル質が結合しているため、X線で検査を行って、2つの歯根が確認され、初めて癒合歯とわかることもあります。
✅ 原因
明確な原因は不明だが、胎児期の発育異常や遺伝的要因が関係している
✅ 影響
基本的に痛みがなければ経過観察で問題ないことがありますが、むし歯になりやすい形状をしているため、注意が必要です。永久歯への影響が懸念される場合や、見た目や噛み合わせに影響がある場合は治療対象になります。
癒着歯とは
癒着歯とは、歯の表層にあるセメント質のみが骨とくっついている状態を指します。これは癒合歯や双生歯に比べて結合が浅く弱いため、生え変わりの時期に一方の歯だけが抜けて、癒着が自然に外れるケースもまれにあります。また、歯の内部の神経や象牙質が露出することはないため、冷たいものなどによる刺激でしみるといったような痛みは起こりにくいのが特徴です。
✅ 原因
明確な原因は不明ですが、胎児期の発育異常や遺伝的要因が関係している
✅ 影響
永久歯への生え変わりに影響を及ぼさず、咬み合わせや見た目に支障もなく、痛みや炎症などの症状が出ていない場合は治療を必要としません。ただし、永久歯が正しく生えてこない埋伏(まいふく)異常や位置異常があったり、隣の歯や噛み合わせに影響を与えていると、咬合力の不均衡により他の歯に負担をかけている状態です。歯の寿命や顎の成長に悪影響がある場合は、抜歯や矯正治療が必要となります。
双生歯
1つの歯胚が2つに分離して成長発育した状態です。癒合歯と発生過程は異なりますが、見た目は似ているため、癒合歯か双生歯か診断が困難なことがあります。
歯の形成不全とは
歯の形成不全とは、歯が正常に発育及び発達しない状態を指します。歯の表面のエナメル質や内部の象牙質などがうまく作られず、歯の形や色、硬さなどに異常が見られる状態です。
エナメル質形成不全
歯の表面が白く濁りまだらになっている状態です。白いエナメル質が黄から褐色に変色し、凹凸や欠けがありザラザラしています。
象牙質形成不全
象牙質がうまく作られず、歯がもろく変色しやすい遺伝性の病気です。Shields I型(骨形成不全症を伴い骨と歯に症状)、Shields II型(骨には異常なしで歯のみ症状)があります。
歯根が短く神経の空間が早く閉じるため痛みは出にくいですが、乳歯・永久歯のどちらでも、エナメル質がはがれやすく歯がすり減ります。琥珀色で透明感のある歯で、一部または全体の歯に生じることがあり、左右対称にみられることが多いです。
✅ 原因
- 先天性の遺伝
- 幼少期の病気や高熱
- 栄養不足、外傷、薬剤(テトラサイクリンなど)
- 歯の発育時期の環境的影響
✅ 注意点
形成不全の歯は虫歯になりやすく、知覚過敏や咬む力の弱さにもつながるため、早期の診断と治療(レジン補修・クラウンなど)が大切です。
結節の異常とは
結節の異常とは、歯の表面にある通常より大きい、あるいは異常な形の突起(結節)に関する問題を指します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| タロンカスプ(切歯結節) | 上の前歯の裏側に現れる突起。咬み合わせや発音に支障をきたす可能性 |
| 中心結節 | 小臼歯の咬合面中央に現れる突起。折れや割れがあれば神経に達し、早期に治療が必要 |
| カラベリー結節 | 上の奥歯の裏側に現れる突起。破折しにくいが、清掃性が悪く細菌感染のリスク |
結節の異常は、不正咬合や顎関節症の原因になり、審美的な問題で気になることも多いです。不快感やリスクがなければ経過観察ですが、結節が折れたり、咬合に支障がある場合は削除やレジンによる補強を行います。破折のリスクがあり、神経への影響も懸念されるため、神経に影響が出た場合は根管治療が必要になることもあります。
歯根の形態異常とは
歯の根の形の異常にはいくつかの種類があります。見た目ではわからないためレントゲンやCT検査で発見されることが多いです。
- 極端に曲がった歯根彎曲(しこんわんきょく)
- 複数の根がくっついて大きな塊になり、C字型や馬蹄形になる樋状根(といじょうこん)
- 複数の根がくっつき台形になる台状根(だいじょうこん)
- 先天的に歯根が短い短根(たんこん)
このような歯根の形態異常があると、矯正治療で歯を動かすのが難しくなることがあります。
歯の形が悪い時の治療法
治療方法としては、審美性や機能性の改善が主な目的となります。
| 異常の種類 | 主な治療法 |
|---|---|
| 矮小歯 | 補綴(ベニアやクラウン)、矯正によるバランス調整 |
| 巨大歯 | 歯冠形成、矯正治療、必要に応じて抜歯 |
| 癒合歯 | 矯正治療、審美的問題があれば補綴や抜歯 |
| 癒着歯 | 経過観察、生え替わりに問題がある場合は抜歯・矯正 |
| 歯の形成不全 | レジン修復やクラウン、知覚過敏ケア、予防管理 |
| 結節の異常 | シーラントや咬合調整、破折時は根管治療 |
| 歯根の形態異常 | 慎重な管理、CT診断、矯正や根管治療の際は専門医対応 |
まとめ

歯の形が悪いとお悩みの場合、見た目以外に噛み合わせに影響することが多いため、早期の歯科受診をおすすめします。治療には複数の選択肢があり、歯科医師と相談しながら症状や希望に合った方法を選ぶことが大切です。気になる歯があれば、歯科医院を受診し、相談や検査を受けましょう。